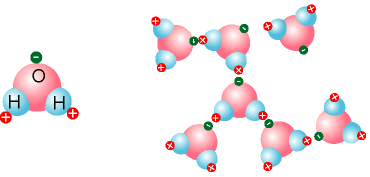|
|
|
|
7、水、不思議な地球の贈り物
前回、限定された平面に固定された画像は新しい視点を与えてくれる、という話をしましたが、限定されないと、形さえ作ることができないのは、「水」ですね。もっとも液体はどれもそうですが、水は身の回りに普通にあって、自然の中でも極めて重要な役割を果たしている物質ですから、今日は「水」をめぐる、美術と科学の話をしましょう。 絵を描き始めて、最初の頃にぶつかる一つの壁が「水」の表現かもしれません。海や川、グラスに注がれた水など、その透明でありながら存在感のある水を、どうやって描けば良いのか… 子供の頃のように、水色で塗って済ませるわけには行かなくなると、ちょっと悩んでしまいます。 アニメなどでも、昔の作品ではコップに入った水などは、水色で塗って済ませていますが、最近のものでは、反射光を描いてきちんと透明に描いています。 この反射光を描く、というのが透明なものを表現する一つの手段なんですが、前回の円筒形の底と同じで、「水は透明」という固定概念があると、真っ白な反射光を描くというところへ、なかなか辿り着きません。 水を表現するには、反射光以外にも、透けて見える物が屈折している様子や、深くなるにつれて暗くなっていく様子、さざ波や揺らぎなど、よく観察しなければ描けない状態のオンパレードで、絵を描く面白さと難しさが詰まっています。 自然科学でも、「水」は非常に特別な存在です。地球上の生物は、水から生まれ体内に水を入れて生きています。細胞は水をベースとした水溶液で満たされた袋で、生体反応は水溶液中で行われます。 通常の化学反応の多くは、高温高圧下で進むのですが、生体反応は普通の温度で、特に圧力をかけなくても進みます。これは酵素というタンパク質によるものですが、生体物質の化学反応が水の中で行われるというのも、生物の特色の一つです。 水の分子は、水素原子2つと酸素原子1つが結びついたものですが、これは極性分子と呼ばれ、水の分子一つが棒磁石のように、両側が+-という性質を持っています。 これによって、非常に強い表面張力があったり、0度Cになると、金属のように結晶になったり、という独特の性質を持つことになります。 水の分子はこんな感じ↓ 植物にとっては、この表面張力が重要です。高い木のてっぺんまで、地面から水を吸い上げることができるのは、水の強い表面張力のおかげです。水分子は互いに引き合う力が強いので、一つながりとなって、ずるずると引っ張り上げられるのです。 水はこれほどまでに表面張力が強いので、空間に放り出されると、球になりますね。うちには、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の大きな波をプリントした鏡があるのですが、この絵を見ていると、北斎の動態視力って凄いよナ、と思ってしまいます。波がくだける瞬間に、水玉になったしぶきが飛んでいる様子は、見えているようではっきり見えない状態だと思うんです。今なら、それこそ写真に撮って確認できますが… |
水のなんでも小事典 盛岡 通 (著) 講談社(1989/10) 赤ちゃんの体は77パーセントが水。これが大人になると約60パーセントに。歳をとるともっと少なくなって、まさに水とともに生命は栄え、また枯れてゆく…。水なくしては地球上に生命は芽ばえず、水なくしては日々の暮らしもなりたたず、うまい水なくしてはうまい料理もありえず…というわけで、水にまつわる面白話を50テーマ集めてみました。
大久保 純一 (著) 小学館 (2005/08) 「自然」「構図」「場所」「旅」「営み」と、主題に即した5つの視点で46枚の全図版を分類し解説。描かれた景観に隠された北斎のねらいや、人物のしぐさ、図像について読み解く。『冨岳三十六景』が描かれた背景と、北斎の生涯・画業についてもよくわかる。 |